薬のしくみ
いろいろな形のくすり
くすりには飲む薬、注射する薬、貼る薬、塗る薬などその使い方により、いろいろな形があります。飲む薬にも、錠剤やカプセル、散剤(粉薬)などがありますが、これは薬の成分が効率よく吸収され、目標の場所にタイミングよく到達するようにいろいろな形の薬があるのです。
今回は、特に飲み薬についてお話します。
飲み込んだくすりは、主に腸で吸収されて効果を現します。形としては、錠剤、散剤、水薬などがあります。
- 錠剤のいろいろ
内服用錠剤のメリットには、飲みやすい・含有量が均一・効果時間が調節できる・味を良くしたり臭いを消すことができる などがあります。
| 裸錠 | 成分にデンプンや乳糖を加え、そのまま錠剤にしたもの。 |
|---|---|
| 糖衣錠・フィルムコーティング錠 | 味の悪い薬の表面を砂糖などで覆い、飲みやすくしたもの。 |
| 腸溶錠 | 胃で溶けると効き目が悪くなったりする薬の表面をセルロースで覆い、酸性の胃で溶けないで腸で溶けるようにしたもの。 |
| 持続性錠 | 薬の効果を長時間持続させるために特殊加工したもの。 |
散剤は錠剤やカプセル剤に比べ腸からの吸収が速く効果がすぐに現れるのが特長です。顆粒剤は味のよくない成分の表面を薄い膜で覆ったり、膜の厚みなどを変えて、成分が溶け出す時間を調節したりできるのが特長です。
>カプセル剤味や臭いの悪い薬をゼラチンなどで作ったカプセルに入れ、飲みやすくしたものです。消化管の中では比較的速く崩れて放出されます。硬カプセルは中に散剤や顆粒剤を入れ、軟カプセルは中に液体の薬を入れることができます。
>水薬くすりを水や少量のアルコールなどで溶かしたもので、子供が飲みやすいように甘みや香りをつけているものがあります。固形の内服薬と比べ、腸からの吸収が速いのが特長です。
体の中の薬(飲み薬)
飲み込んだくすりは体の中でどうなるのでしょうか。
-
>吸収
- 分布
体の中に入ったくすりは腸で吸収されたあと、肝臓を経て体内を循環する血液に入ります
その後、血液の流れに乗って移動し、毛細血管を通り抜け各組識の細胞へ広がります
>代謝そしてくすりは肝臓を通過する時に分解されます
>排泄肝臓から胆汁中へ、腎臓から尿中へと排泄されます
こうしたくすりの動きのうち吸収と分布は効き目の速さに関係し、代謝と排泄は効き目の持続時間に関係します。つまり、速く吸収・分布されれば、効き目が速くなり、代謝と排泄が遅ければ、効き目が長持ちするのです。
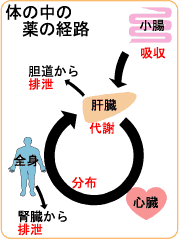
くすりの作用するしくみ
体内に入ったくすりが作用するしくみにはいろいろなものがあります。
物理・化学的性質によって作用するもの、体内で化学反応を助ける酵素の働きを防ぐもの、細胞膜にあるイオンチャンネルに作用して効果を現すものなどがあります。
大部分のくすりは、細胞膜にある受容体(レセプター)に作用して効果を現します。受容体には通常、体内で産生されるホルモンや神経末端から放出される科学物質が結合し、 細胞が反応して体の活動が維持されていますが、くすりの作用のしかたには、この受容体を刺激し細胞に反応を起こしたり(作用薬)、受容体と結合することによって本来生じる反応を遮断する(拮抗薬)、という2種類の作用があります。
